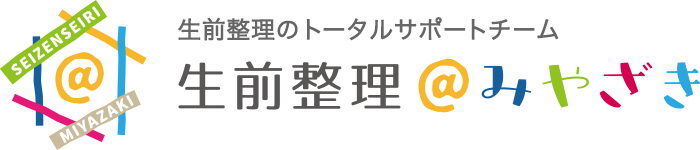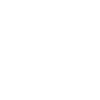あの日の青い空
2007/08/15
外地に送られる前、滋賀県の兵舎にいた父も
宮城県仙台市から少し離れたところに疎開していた女学生だった母も
埼玉県幸手に疎開していた祖父母も
宮崎市内で小学校の先生をしていた舅も
鳥取県で軍の教育隊の仕事をしていた姑も
中国北京あたりに出兵していた隣家のおじも
宮崎市郊外の農家にいた隣家のおばも
みんな「目にしみるような青い空だった」と言う。
子供のころ、巣鴨のお地蔵さんの縁日にいくと、必ず、手足のない”傷痍軍人さんたち”が白い軍服をきて道端に座り、アコーディオンを悲しげに奏で、お金を恵んでもらっていた。
終戦の少し前、私が今住む家の近くを、おばの同級生が学校へむかっていたら、どこからともなく敵の飛行機が飛んできて、彼女を追い掛け回し、ひとつだけ落とした爆弾にあたって死んだそうだ。
終戦の日の天気が、そろいもそろって『青い空』というのはちょっと疑問だが、「負けた」というより、「やっと終わった」という気持ちが、目に写るものとして記憶に残っているのではないか、と思った。
「私は息子を戦争で死なせるために生んだのではない。だから、これで戦争はしないと誓った憲法を見たとき、ほんとうにすばらしい文だと思ったの」
明治時代に生まれ、ごくごく普通の日本の女性として生きてきた祖母のこの言葉、私は終生忘れない。